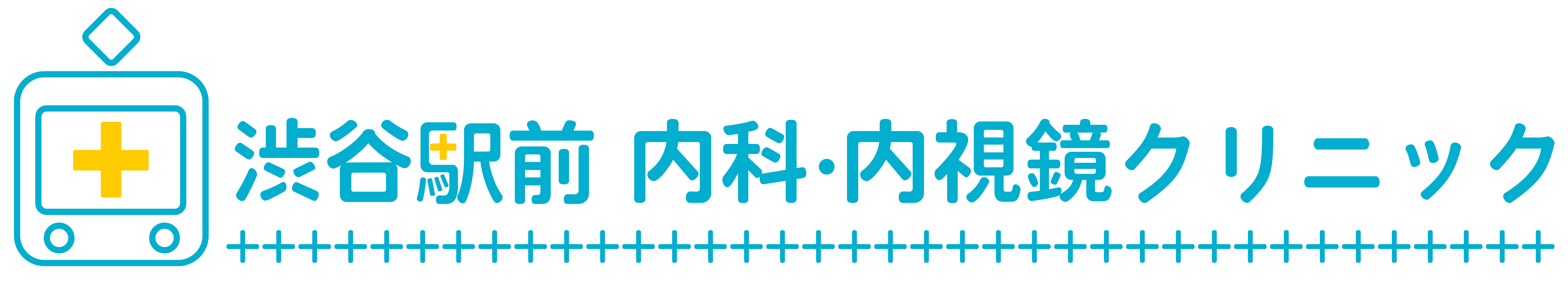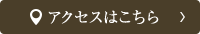このような血便症状はありますか?
- 便に血が混じっていた
- 便器が真っ赤に染まる
- 下痢の中に赤いものが混ざっている
- トイレットペーパーで拭いたら血が付いていた
- お尻から血が垂れている
血便とは
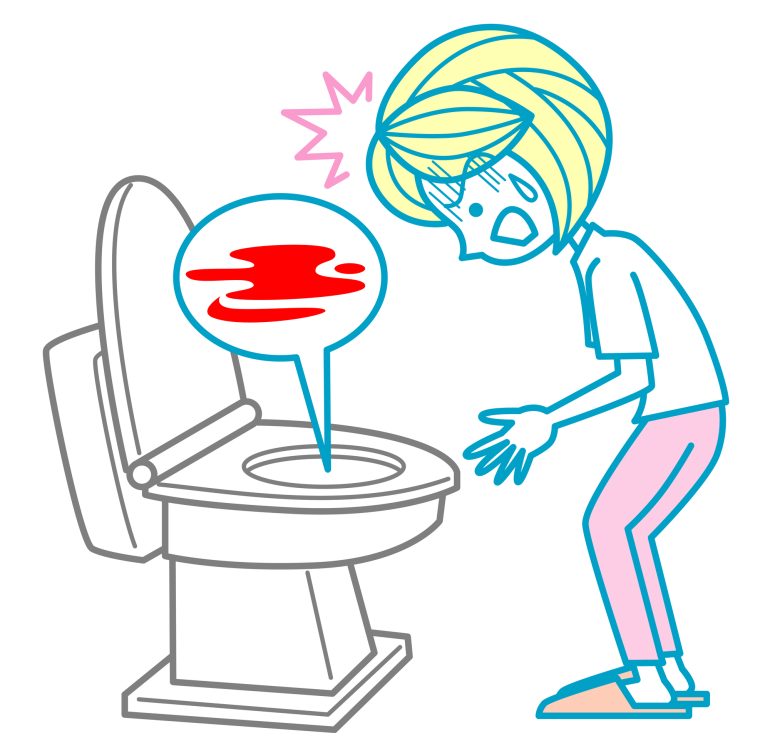 便に血が付着している、トイレットペーパーに血が付く、便器が血で真っ赤に染まる、肛門から血がポタポタ垂れるなど血便の症状は様々です。
便に血が付着している、トイレットペーパーに血が付く、便器が血で真っ赤に染まる、肛門から血がポタポタ垂れるなど血便の症状は様々です。
血便症状は、消化管から肛門のどこかで出血が起こっているので、詳しく検査する必要があります。血便は、いぼ痔や切れ痔の他に、大腸がんや前がん病変の大腸ポリープ、炎症性腸疾患などの可能性もあるので、原因疾患を調べて適切な治療を行いましょう。
血便が起こりやすい疾患
- 胃潰瘍
- 胃がん
- 十二指腸潰瘍
- 虚血性腸炎
- 薬剤性腸炎
- 大腸憩室出血
- 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)
- 大腸ポリープ
- 大腸がん
- 切れ痔
- いぼ痔
など
血便は放置せずに消化器内科を受診しましょう
血便がでても、痔だと油断してそのまま放置してしまうと大腸がんなどの重篤な疾患を見逃してしまう恐れがあります。血便は、見た目ではっきりとわかるものだけでなく真っ黒い便や目に見えないほど微量な血液が混じる便潜血などもあります。いつもと便の色が違う、便潜血検査で陽性がでた、血便の他に発熱や貧血、腹痛などの症状がある場合、早めに内視鏡検査に対応している消化器内科を受診しましょう。
当院は、鎮静剤を使用して苦痛を抑えて楽に受けられる上部内視鏡検査(胃カメラ検査)・下部内視鏡検査(大腸カメラ検査)を行っています。気になる症状がある方は、お気軽にご相談ください。
血便の種類
鮮血便
鮮やかな真っ赤な血便で、お尻を拭いたときに血が付く、便器が真っ赤に染まるなどの状態です。肛門の近くで出血していることが原因で、いぼ痔や切れ痔、直腸がんなどが疑われます。直腸や肛門を調べる必要があります。
粘血便
粘り気のある血液が便に混ざった状態で、いちごジャムなどに例えられることがあります。赤痢アメーバなどの感染症、潰瘍性大腸炎・クローン病などの炎症性腸疾患などが考えられます。粘血便は、原因を調べるために下部内視鏡検査(大腸カメラ検査)を行います。
暗赤色便
褐色のレンガ色のような血便です。大腸、小腸付近に出血が起こって、時間の経過とともに消化液が混ざり合って暗赤色になります。炎症性腸疾患や大腸の感染症、大証憩室出血などが疑われます。腹部超音波検査や下部内視鏡検査(大腸カメラ検査)を行い、大腸粘膜の状態を確認する必要があります。
黒色便(タール便)
食道、胃、十二指腸のどこかで出血が起こると、胃酸と混じって真黒な便が出ます。
出血量が多いと貧血や血圧低下、出血性ショックなどを引き起こすことがあります。
徐々に出血していると、体が疲れやすい、倦怠感、だるさなどの症状がみられます。主な原因は、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんなどが考えられます。真っ黒い便がでたときは、上部内視鏡検査(胃カメラ検査)を行い、出血している場所を確認する必要があります。
また、貧血治療で鉄分の薬を飲んでいると副作用で黒い便が出ることがあります。
血便の検査
直腸診
鮮血便や粘血便が出たときに、いぼ痔や切れ痔、肛門者直腸の腫瘍などの有無を確認するために行います。肛門周囲に血液が付着しているかどうか、血液の色や量などを確認します。
上部内視鏡検査(胃カメラ検査)
 食道、胃、十二指腸の粘膜から出血が起こって黒い便がでた際に、出血している場所を特定するために行います。上部内視鏡検査(胃カメラ検査)は、粘膜の出血の他にも炎症や潰瘍の有無、ピロリ菌に感染しているかどうかなどを調べることができます。当院は、鼻から行う経鼻検査と口から行う経口検査からお選びいただくことができます。
食道、胃、十二指腸の粘膜から出血が起こって黒い便がでた際に、出血している場所を特定するために行います。上部内視鏡検査(胃カメラ検査)は、粘膜の出血の他にも炎症や潰瘍の有無、ピロリ菌に感染しているかどうかなどを調べることができます。当院は、鼻から行う経鼻検査と口から行う経口検査からお選びいただくことができます。
下部内視鏡検査(大腸カメラ検査)
 粘血便や暗赤色便の症状は、大腸からの出血が疑われるため、大腸全域の粘膜を調べることができる下部内視鏡検査(大腸カメラ検査)を行います。下部内視鏡検査(大腸カメラ検査)は、粘膜の出血を確認するだけでなく検査中に見つけた大腸ポリープの切除や止血処置、潰瘍の有無などを調べることができます。疑わしい病変は、組織を一部採取して病理検査を行うことで確定診断が可能です。
粘血便や暗赤色便の症状は、大腸からの出血が疑われるため、大腸全域の粘膜を調べることができる下部内視鏡検査(大腸カメラ検査)を行います。下部内視鏡検査(大腸カメラ検査)は、粘膜の出血を確認するだけでなく検査中に見つけた大腸ポリープの切除や止血処置、潰瘍の有無などを調べることができます。疑わしい病変は、組織を一部採取して病理検査を行うことで確定診断が可能です。
当院で行う下部内視鏡検査(大腸カメラ検査)は、鎮静剤を使用して痛みに配慮して楽に受けられます。
血便の予防
定期的に検査を受けましょう
胃がんや大腸がんは、初期の頃は自覚症状が乏しく、血便などの症状がでた頃には、状態がかなり進行している可能性があります。胃がんや大腸がんは、早期発見ができれば内視鏡による治療で完治が見込めます。
特に、胃がんや大腸がんの発症リスクが高くなる40歳を過ぎたら、定期的に内視鏡検査を受けましょう。
ピロリ菌の除菌治療
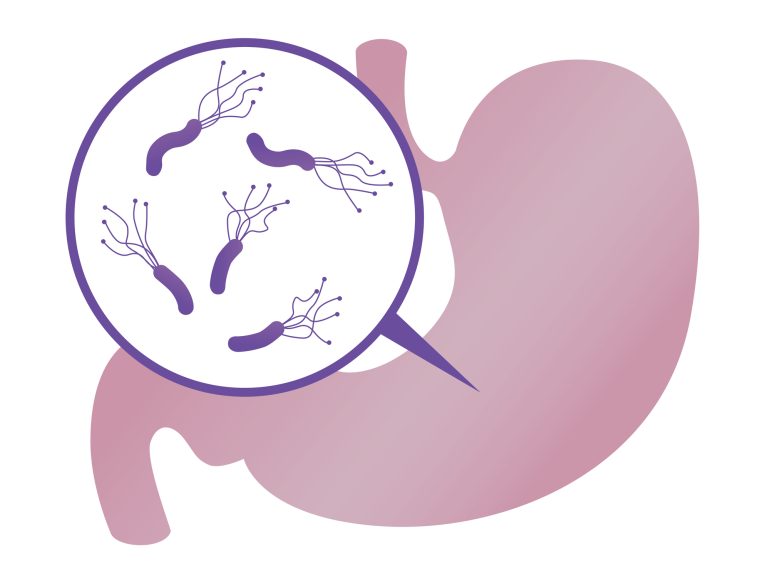 ピロリ菌は、慢性胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんなどの原因となるため、感染していることがわかったらすぐに除菌治療を行いましょう。
ピロリ菌は、慢性胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんなどの原因となるため、感染していることがわかったらすぐに除菌治療を行いましょう。
ピロリ菌に感染していると、血便症状が起こる疾患に罹るリスクが高くなるので、除菌治療を行うことで血便の予防につながります。
便秘の改善
便秘を繰り返していると、硬い便が通過することで肛門や直腸が傷ついていぼ痔や切れ痔が起こりやすくなります。便秘の原因は、食生活や生活習慣、ストレス、水分不足など様々ですが、適切な治療を行うことで便秘を解消することが可能です。
便秘を改善することで、血便だけでなく肛門疾患、大腸疾患の発症予防にもなりますので、便秘でお困りの方はお気軽にご相談ください。