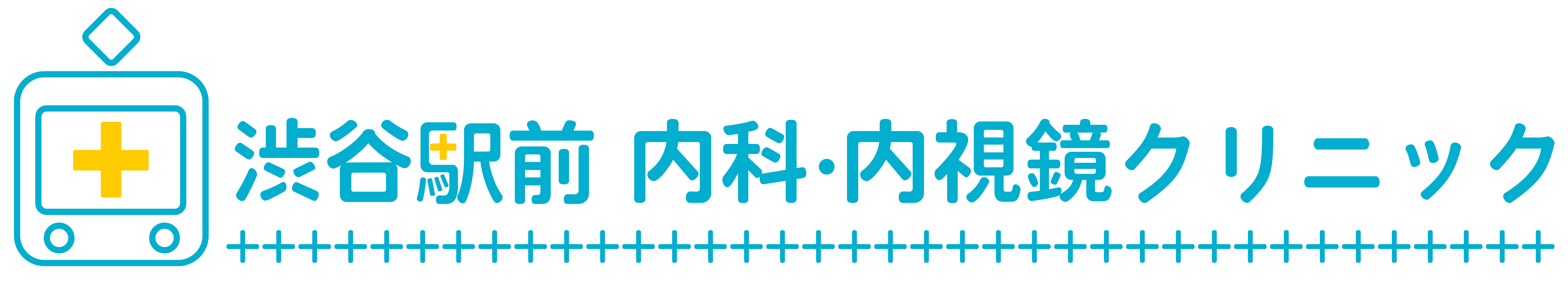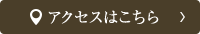ウイルス性肝炎とは?感染経路・原因と症状
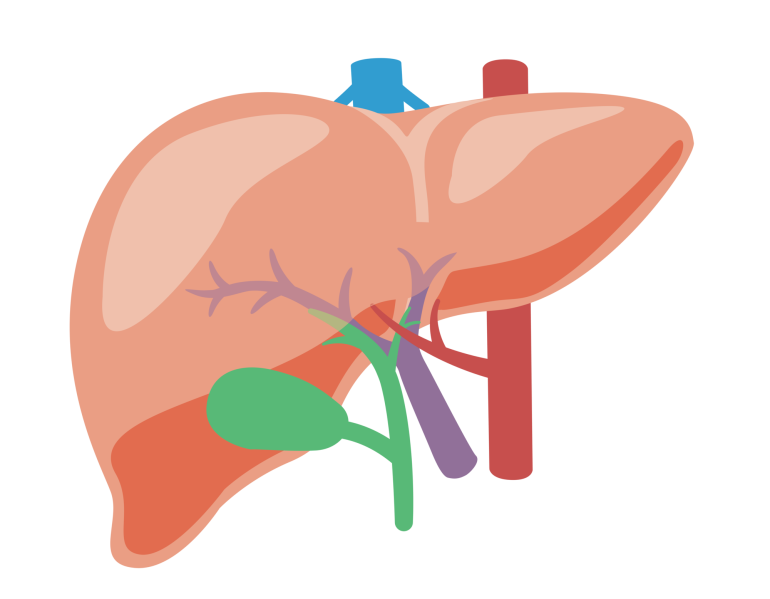 ウイルス性肝炎は、ウイルスのタイプ別にA、B、C、D、E型に分けられます。症状がほとんど現れないものや、突然の炎症から数週間にわたって症状が続く場合もあります。
ウイルス性肝炎は、ウイルスのタイプ別にA、B、C、D、E型に分けられます。症状がほとんど現れないものや、突然の炎症から数週間にわたって症状が続く場合もあります。
風邪に似たような症状や喫煙者はタバコの味が変わる・まずく感じるような症状など、現れる症状は様々です。炎症が続いて肝機能が低下すると、肝不全を起こして命の危険があるので注意が必要です。
急性ウイルス性肝炎を発症すると、3~8週間ほどで肝機能は回復するので、特に治療の必要はありません。ウイルス性肝炎を発症しても自覚症状が無い方は、気が付かないうちに周囲へ感染を広げている可能性があります。定期的に検査を行いましょう。
A型肝炎ウイルス(HAV)
A型肝炎ウイルス(Hepatitis A virus、HAV)の感染経路は、感染者の排泄物や血液が手や水、食品を介してウイルスの感染が広がります。症状は、発熱、疲労、食欲不振、腹痛、黄疸などがあります。通常は、自然に回復しますが稀に重症化することもあります。
A型肝炎ウイルスは、ワクチン接種が効果的です。他のウイルス性肝炎とは異なり、慢性化することはありません。
B型肝炎ウイルス(HBV)
B型肝炎ウイルス(Hepatitis B virus、HBV)は、感染者の血液または体液を介して感染します。
感染経路は、ウイルスに感染している母親から生まれてくる子供への母子感染、汚染された注射具の共有、輸血、性行為などの水平感染があります。B型肝炎ウイルスによって引き起こされる肝炎は、「一過性感染」または「持続感染」のいずれかに分けられます。一過性の急性肝炎は、疲労、発熱、関節痛、黄疸、尿の色が濃くなるなどの症状があります。自覚症状が無い場合もあり、気が付かないまま自然治癒することがあります。胆汁の流れが滞留すると、全身のかゆみや便の異常を引き起こす胆汁うっ滞が起こることがあります。黄疸などの症状は、2週間ほどでピークを迎え、その後数週間かけて消失します。
「持続感染」の慢性肝炎は、感染が長期にわたって続く状態です。適切な治療が行われないままでいると、肝硬変や肝臓がんなどの合併症を引き起こす可能性があります。稀に劇症肝炎を生じることがあり、肝機能が低下すると血液を固める凝固因子が生成されず、体内に有毒な物質が血液を介して脳に運ばれると、肝性脳症を引き起こす恐れがあります。
C型肝炎ウイルス(HCV)
C型肝炎ウイルス(Hepatitis C virus、HCV)は、感染者からの血液感染が主な感染経路です。過去に、輸血や血液製剤を使用した経験がある方、感染者との性交渉、刺青や覚せい剤の使用が主な原因ですが、稀に出産時の母子感染などがきっかけで感染することがあります。C型肝炎ウイルスは、ほとんどが無症状ですが腹痛や疲労感、黄疸、食欲低下などの症状が出ることもあります。次第に、慢性化すると黄疸、腹水、体重減少、肝性脳症などの自覚症状が現れます。進行すると肝硬変や肝臓がんなどの合併症を引き起こすので、早めの治療が重要です。
D型肝炎ウイルス
D型肝炎ウイルス(Hepatitis D virus、HDV)は、単独で感染することはありません。B型肝炎ウイルスと同じ感染経路を通じて同時感染します。D型肝炎ウイルスは、重篤になりやすく慢性肝炎から肝硬変、肝臓がんなどの合併リスクも高いため注意が必要です。
日本国内での発症数はほとんどなく、感染者の多くは、南ヨーロッパを中心とした欧米諸国です。
E型肝炎ウイルス
E型肝炎ウイルス(Hepatitis E virus、HEV)の主な感染経路は、猪や鹿などの排泄物や加熱不足の肉などを介して経口感染します。発熱、疲労、腹痛、関節痛、食欲不振、黄疸などの症状があります。一過性の急性肝炎として発症して、しばらく安静に過ごすことで自然に治癒します。妊婦の方は、重症化することがあります。
ウイルス性肝炎の潜伏期間
| A型肝炎 | B型肝炎 | C型肝炎 | D型肝炎 | E型肝炎 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 潜伏期間 | 15~50日 | 30~180日 | 15~180日 | 30~180日 | 15~50日 |
| 慢性化 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| ワクチン | 〇 | 〇 | × | × | × |
A型肝炎
ウイルスに感染してから、2~6週間で発病します。予防接種で未然に感染を防ぐことができます。A型肝炎は、衛生環境の良くない地域に旅行することで感染することがあります。感染リスクのある地域への渡航の際は、事前にワクチンを打つようにしましょう。
B型肝炎
ウイルス感染後、1~6か月後に発症します。感染してもしばらく症状が出ない場合があります。B型肝炎は、予防接種によって感染を防ぐことができます。
C型肝炎
潜伏期間は、2週間~6ヶ月で、C型肝炎ウイルスに感染すると、ほとんどの方は、自覚症状が無いため気が付かないうちに慢性肝炎や肝硬変、肝臓がんへと進行していきます。
E型肝炎
潜伏期間は、3~8週間程度で、A型肝炎と同じく急性肝炎として発症します。
ウイルス性肝炎の検査
- 健康増進法に基づく健康増進事業による肝炎ウイルス検査
- 特定感染症検査等事業による保健所等における肝炎ウイルス検査
国が定める精度によって、各自治体で①②の肝炎ウイルス検査を受けることができます。
また、企業健診で肝炎ウイルス検査を受けることもできます。医療機関によっては、出産・手術前の検査として肝炎ウイルス検査を実施しているところもあります。
ウイルス性肝炎の治療
A型肝炎ウイルス
ほとんどの場合、安静に過ごすことで自然に回復していきます。
食欲不振などの症状が見られる場合は、薬を処方する場合があります。
B型肝炎ウイルス
ウイルスの活動を抑制する抗ウイルス薬を処方します。現在の治療では、ウイルスを完全に排除することは難しいため、治療は肝機能障害を防いで肝硬変や肝臓がんなどの重篤な疾患を発症しないようにすることを目的に行います。
治療中は、定期的に肝機能検査やウイルス量を観察していくことが大切です。
C型肝炎ウイルス
ウイルスの活動を抑制する抗ウイルス薬を処方します。C型肝炎ウイルスの主な治療は、完全にウイルスを体内から排除する直接作用性抗ウイルス薬が用いられます。
E型肝炎ウイルス
A型肝炎ウイルスと同様に、安静にしていることで自然治癒することがほとんどです。
食欲不振など気になる症状がある場合、その症状に合わせた薬を処方することがあります。
ウイルス性肝炎の完全を防ぐ予防法
 A型肝炎、B型肝炎は、ワクチンが開発されているので、ワクチン接種によって感染を予防することができます。
A型肝炎、B型肝炎は、ワクチンが開発されているので、ワクチン接種によって感染を予防することができます。
衛生状態が悪い場所で水をそのまま飲む等、A型肝炎・E型肝炎の感染リスクが高まる行動は控えましょう。水はしっかり煮沸する、疑わしい食材も加熱処理をしてから食べるようにしましょう。
体液や血液を介して感染する恐れがあるB型肝炎・C型肝炎の予防として、性交渉の際のコンドームの使用、感染者との歯ブラシの共有を避ける、他人の血液を直接触らないなどの対策が効果的です。
感染者が妊娠した場合、生まれてくる子供への感染を防ぐために出産時にワクチンや免疫グロブリン製剤などを使用します。