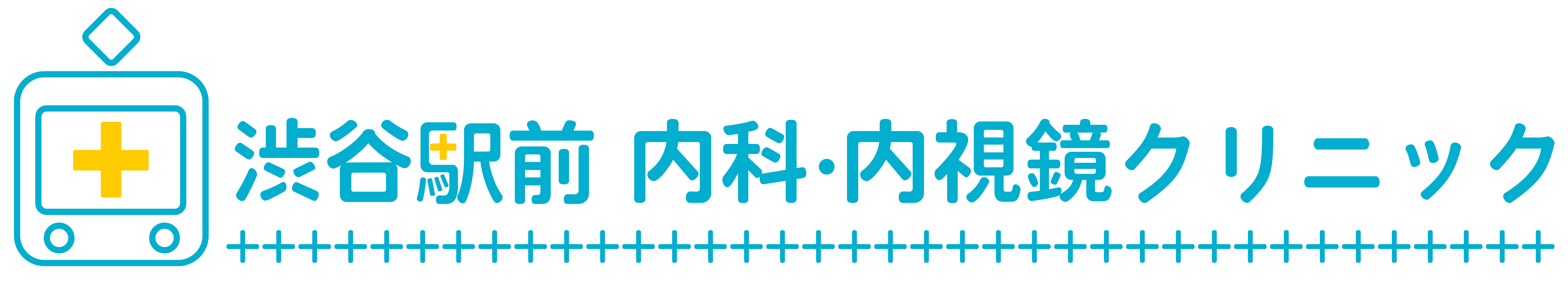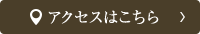C型肝炎(HCV)とは
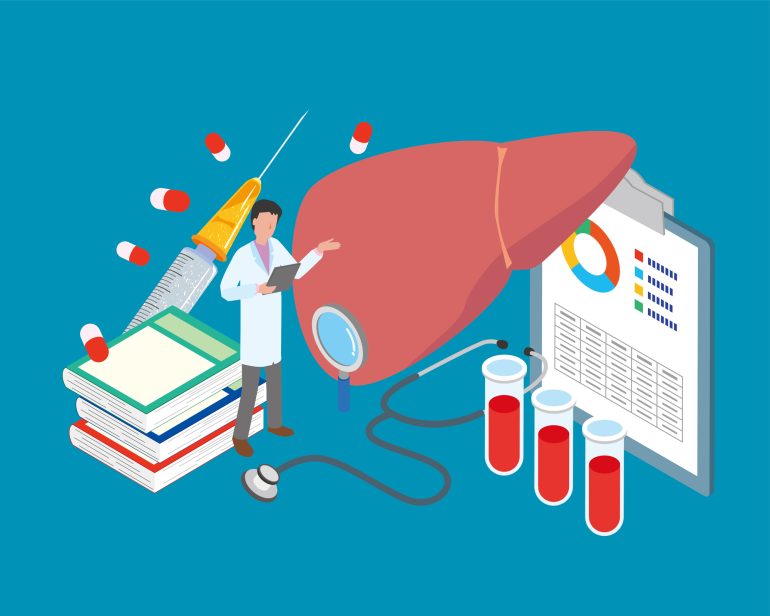 C型肝炎(Hepatitis C、HCV)は、C型肝炎ウイルス(Hepatitis C virus)によって引き起こされるウイルス性の肝疾患です。C型肝炎は、主に感染者の血液を介して感染しますが、感染者の体液に接触することで感染することもあります。C型肝炎は、急性期にはほとんど症状が無く、気が付かないうちに慢性肝炎に進行することがあり、肝硬変や肝がんなどの重篤な合併症を引き起こす可能性があります。
C型肝炎(Hepatitis C、HCV)は、C型肝炎ウイルス(Hepatitis C virus)によって引き起こされるウイルス性の肝疾患です。C型肝炎は、主に感染者の血液を介して感染しますが、感染者の体液に接触することで感染することもあります。C型肝炎は、急性期にはほとんど症状が無く、気が付かないうちに慢性肝炎に進行することがあり、肝硬変や肝がんなどの重篤な合併症を引き起こす可能性があります。
肝臓疾患は自覚症状が無いまま進行するため、「沈黙の臓器」とも呼ばれる肝臓ですが、進行のスピードには個人差があり、さらに年齢や性別にも関係しています。慢性肝炎の発症から肝硬変へと進行するのに20年前後、肝硬変から肝臓がんへと進行するのに10年前後かかる傾向があります。国内では、およそ150万人のC型肝炎ウイルス感染者がいると予測されています。自覚症状が無いので、知らない間に感染を広げている可能性があります。
C型肝炎の感染経路
C型肝炎はRNAウィルスで主な感染経路には、以下のような状況が考えられます。
- 針や注射器を共有する
- 血液製品の輸血(以前は主要な感染経路でしたが、現在はより安全なスクリーニングが実施されています)
- 覚せい剤の使用
- 医療処置や美容施術での汚染された器具の使用
C型肝炎の感染者のほとんどは、初期に症状がほとんどまたは全く現れないため、感染者は気が付かない間に慢性肝炎へと移行していることがあります。
呼吸による空気感染や唾液、皮膚の接触では感染することはありません。現在、性交渉や母子感染、輸血後の感染などの可能性は、極めて低くなっています。現時点では、C型肝炎ウイルスを予防する有効なワクチンはないため、感染した血液が体内に入らないように気をつける必要があります。
C型肝炎の潜伏期間と症状
C型肝炎ウイルスの潜伏期間は、2週間~6ヶ月です。感染しても、3割の方は自然治癒しますが、残りの7割は慢性肝炎へと移行します。急性期には、自覚症状がほとんどありません。健康診断などで血液検査を行った際に、感染が発覚する場合が多いです。
慢性肝炎になると黄疸、腹水、体重減少、肝性脳症などの自覚症状が現れます。
慢性肝炎から肝硬変を引き起こすと、食欲低下や全身の倦怠感、むくみ、尿の色が濃くなるなどの症状が見られることもあります。
C型肝炎の検査・診断
 C型肝炎の診断は、採血による血液検査によって行われます。特定の抗体やウイルスのRNAを検出することで感染を診断し、ウイルスのジェノタイプや肝機能の評価などの追加の検査が行われることがあります。
C型肝炎の診断は、採血による血液検査によって行われます。特定の抗体やウイルスのRNAを検出することで感染を診断し、ウイルスのジェノタイプや肝機能の評価などの追加の検査が行われることがあります。
C型肝炎の治療
 C型肝炎ウイルスの治療は、インターフェロンを使用する場合や特定の抗ウイルス薬を使用します。抗ウイルス薬は、ウイルスの増殖を抑制し、患者の状態を改善し、肝臓の損傷を防止するのに役立ちます。最近の治療法では、高い治療成功率を達成し、多くの場合、完全なウイルス除去が可能です。
C型肝炎ウイルスの治療は、インターフェロンを使用する場合や特定の抗ウイルス薬を使用します。抗ウイルス薬は、ウイルスの増殖を抑制し、患者の状態を改善し、肝臓の損傷を防止するのに役立ちます。最近の治療法では、高い治療成功率を達成し、多くの場合、完全なウイルス除去が可能です。
C型肝炎から肝硬変や肝臓がんへと進行するため、早めに適切な治療を行う必要があります。