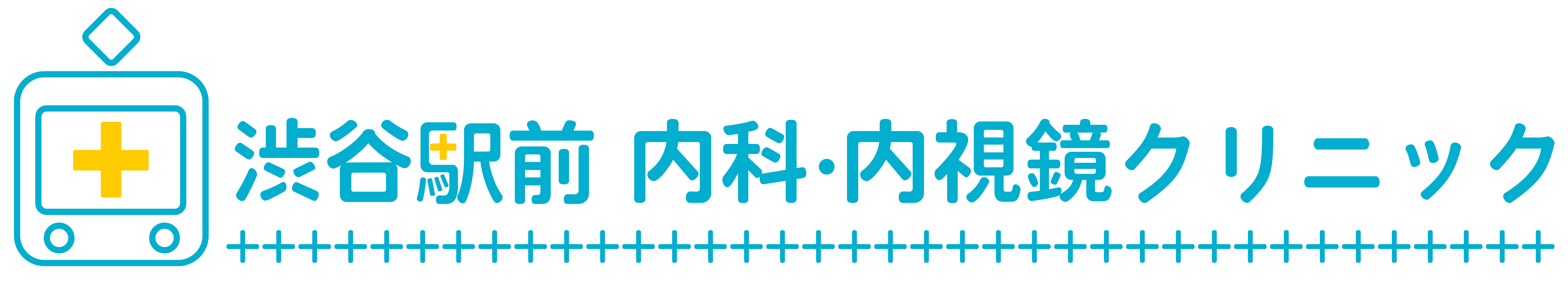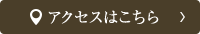このような症状・お悩みはありますか?

- 血便、お尻からの出血がある
- 便秘または下痢が続いている
- 下痢や便秘を繰り返す
- 便が細くなってきた
- 原因不明の貧血
- 残便感、便が残っている感じがある
- お腹の張りが続く
- 腹痛
- 原因不明の体重減少
- 吐き気や嘔吐がある
- 背中が痛い
- 便潜血検査で陽性がでた
大腸がんは自覚症状が乏しいため、このような症状があって大腸がんが見つかった場合、病状がかなり進行していることが多いです。
大腸がんになりやすい年齢・生活習慣とは
大腸がんになりやすい年齢
年齢を重ねるにつれて、発症リスクは高くなります。特に、40歳以上になると大腸がんのリスクは男女ともに高くなります。そのため40歳を過ぎたら、自覚症状が特になくても定期的に下部内視鏡検査(大腸カメラ検査)を受けることで大腸がんの早期発見が可能です。
大腸がんになりやすい生活習慣について
大腸がんは、男女ともに死亡者数が上位で、罹患者数は年々増加傾向にあります。食事の欧米化が大腸がんの発症リスクに影響を与えているといわれています。また、喫煙や過剰なアルコール摂取、肥満、食生活の偏りなども大腸がんのリスクを高めます。また親族に大腸がんを発症した人がいる、大腸腺腫、大腸ポリープがある方は、大腸がんのリスクが高いといわれています。
大腸がんと大腸ポリープ
 大腸ポリープは、ほとんどが良性腫瘍ですが一部の大腸ポリープは大腸がんに進展する可能性があります。
大腸ポリープは、ほとんどが良性腫瘍ですが一部の大腸ポリープは大腸がんに進展する可能性があります。
大腸がんに進展する可能性が少しでもあれば、早めに切除しておくことで大腸がんの予防につながります。
当院では、下部内視鏡検査(大腸カメラ検査)中に発見した大腸ポリープを切除することが可能です。大腸ポリープ切除は、入院の必要がなく日帰りで受けられます。便潜血検査で陽性が出た方、40歳以上の方は、下部内視鏡検査(大腸カメラ検査)を受けましょう。
大腸がんの進行
大腸がんは、ステージで0期、I期、II期、III期、IV期の5段階に分類することができます。癌の深さ、進行度合いを評価して、治療計画に役立てます。
ステージ 0
がん細胞が粘膜上皮内にのみ存在する段階です。周囲の組織には広がっていません。
ステージ I
がんが粘膜や粘膜下層に限局している段階です。リンパ節転移や転移はありません。
ステージ II
がんが周囲の組織や器官に広がり、粘膜や粘膜下層を越えて深く浸潤しています。リンパ節転移や転移はありません。
ステージ III
がんが周囲の組織や器官に広がり、リンパ節に転移しています。腫瘍の進行度合いに応じて、IIIA、IIIB、IIICの3つのサブステージに分類されることがあります。
ステージ IV
がんが他の部位に転移しています。転移先に応じて、IVが複数のサブステージに分類されます。
大腸がんの検査
下部内視鏡検査(大腸カメラ検査)
下部内視鏡検査(大腸カメラ検査)は、肛門からスコープを挿入して大腸粘膜をすみずみまで観察することができます。大腸粘膜に発生する大腸ポリープや大腸がんの位置、範囲、形状、色調を細かく調べることが可能です。検査中に見つけた早期の大腸がんや大腸ポリープは、内視鏡で切除する事もできます。疑わしい病変の一部の組織を採取して、生検を行うことで病気の確定診断を行うことも可能です。下部内視鏡検査(大腸カメラ検査)は、大腸がんの早期発見や予防に役立ちます。
便潜血検査
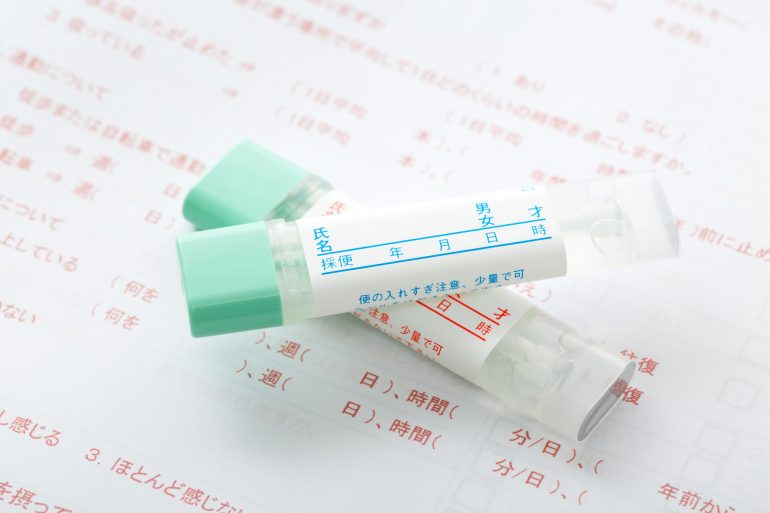 便が大腸を通過する際に、大腸がんに擦れて出血すると便に血が混じることがあります。便潜血検査は、目視では確認できないほど微細な血液も検知することができます。便潜血検査は、便に血が混じっているかを調べる大腸がんのスクリーニング検査なので、大腸がんの診断には下部内視鏡検査(大腸カメラ検査)が必要となります。
便が大腸を通過する際に、大腸がんに擦れて出血すると便に血が混じることがあります。便潜血検査は、目視では確認できないほど微細な血液も検知することができます。便潜血検査は、便に血が混じっているかを調べる大腸がんのスクリーニング検査なので、大腸がんの診断には下部内視鏡検査(大腸カメラ検査)が必要となります。
大腸がんの治療
大腸がんは、ステージや症状、患者さんのお体の状態などによって治療方針を決定します。
内視鏡による治療
内視鏡を用いて、がんを切除する治療法です。開腹を伴う手術と比べて、体への負担が少なく、早期に回復できるメリットがあります。
早期の大腸がんで、がん細胞が大腸壁の内側の粘膜にとどまっている、または粘膜下層の浅い部分でとどまっている状態で行う治療法です。
手術
手術によって、がんが転移する可能性のある部分を含めて切除します。がんを完全に取りきってしまうことで、大腸がんの根治が期待できます。手術は、ステージⅠ~Ⅱが対象となります。場所によっては、人工肛門(ストーマ)が必要となる場合があります。
また、ステージⅢの場合は、手術と併用で再発を防ぐために抗がん剤を使用する術後補助化学療法(アジュバント療法)や放射線治療が必要になります。
化学療法
点滴や内服による抗がん剤治療は、がんの増殖を抑えて進行を遅らせることを目的として行います。手術だけでは取りきれないステージⅣの方が対象となりますが、ステージⅢの手術後の再発を予防するために用いられることもあります。
倦怠感、食欲不振、脱毛、腹痛、下痢、嘔吐、味覚の変化、口内炎、めまい、手足のしびれなど抗がん剤による副作用が起こる場合があります。
放射線治療
放射線を患部に照射してがん細胞を破壊し、大腸がんを消滅または小さくするために行います。その他に、がんの再発予防や再発時の症状緩和のために行うこともあります。
放射線治療は、照射した部分が赤くなる、腹痛、嘔吐、吐き気、下痢、食欲不振、全身の倦怠感などの副作用があります。人によっては、治療から数か月~数年が経って照射部位の異常や頻繁な便意、便失禁などの症状が出ることがあります。