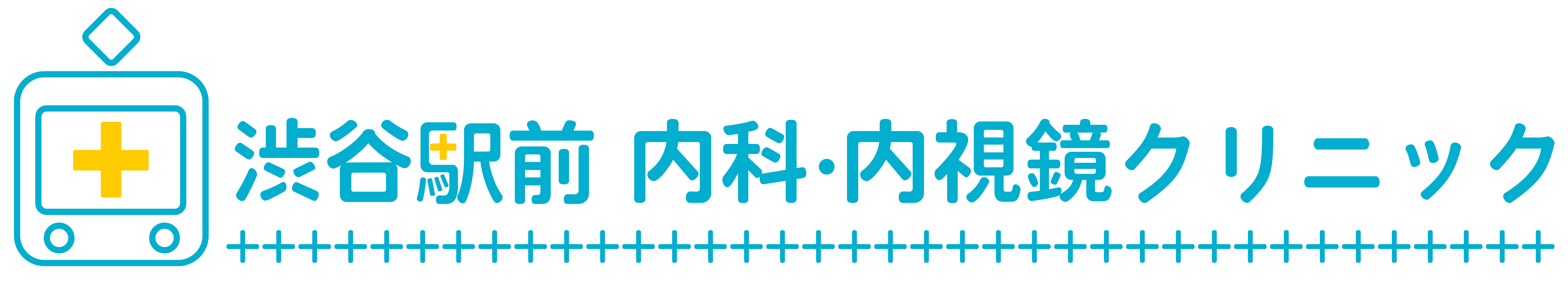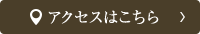肝硬変とは
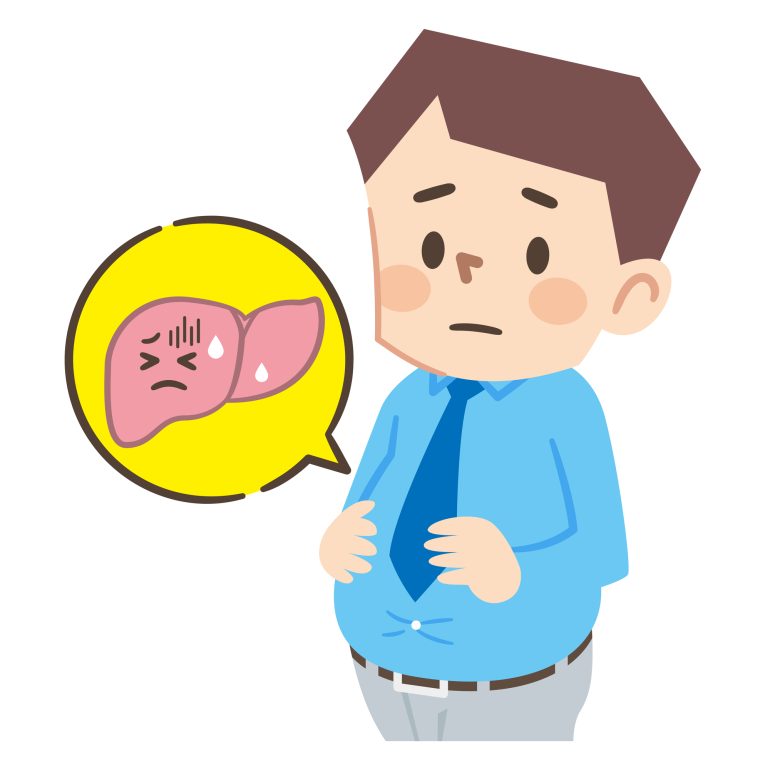 肝炎や肝障害によって肝臓が硬くなってしまった状態です。肝硬変は、慢性肝炎によって肝細胞の破壊と修復作業が長期に渡って繰り返され、肝臓内にかさぶたのような硬い繊維質が蓄積して壁ができることが原因で起こります。
肝炎や肝障害によって肝臓が硬くなってしまった状態です。肝硬変は、慢性肝炎によって肝細胞の破壊と修復作業が長期に渡って繰り返され、肝臓内にかさぶたのような硬い繊維質が蓄積して壁ができることが原因で起こります。
肝硬変になると、肝臓機能が低下して肝臓で作られるアルブミン(タンパク質)や血小板の数が減少していきます。肝機能の低下によって、他の合併症のリスクも高くなるのでなるべく早めに治療を行う必要があります。
肝硬変の主な原因は、C型肝炎
日本人の肝硬変で最も多い原因は、C型肝炎ウイルス感染によるものです。肝硬変の全体の80%ほどといわれています。その他の原因として、アルコールの過剰摂取や薬物による肝障害があげられます。
肝硬変による合併症に注意しましょう
肝硬変は、初期の頃はほとんど自覚症状がありません。次第に、黄疸やむくみ、腹水などの症状が現れて、肝臓がんや胃食道静脈瘤、肝性脳症といった合併症を伴う恐れがあります。
肝硬変が進行すると、肝不全を引き起こすことがあるので、肝硬変の原因となる肝炎や肝障害を早めに治療する必要があります。
肝硬変は、昔は不治の病といわれていましたが初期に適切な治療を行うことで、進行を止めて普段と変わらない生活を送ることができます。肝硬変の合併症を防ぐためにも、早めの治療が重要です。
肝硬変のセルフチェック
このような症状はありますか?
- 体のむくみが気になる
- 目の白目や皮膚が黄色くなるといった黄疸の症状がある
- おなかの張りが続く
- 手のひらが赤い
- 肩などに斑点ができた
- 髪の抜け毛の量が増えた
- 尿の回数が増えた、尿量が増えた
- 体の倦怠感、疲労感、食欲不振などの症状がある
上記の症状に当てはまる方は、肝硬変などの肝臓疾患が原因かもしれません。まずは、肝臓科へご相談ください。
肝硬変の症状
初期症状(代償性肝硬変)
肝硬変は、初期の頃は自覚症状がほとんどありません。無症状の場合が多く、人によっては少し体のだるさや倦怠感、食欲不振などの症状を感じることがあります。
中期~末期症状(非代償肝硬変)
肝硬変が進行していくと、以下の症状が現れます。
黄疸
血液の中のビリルビンが上昇して、皮膚や目の白い部分が黄色くなります。
腹水・浮腫
血液中のたんぱく質が減少することによって、お腹の張りや手足のむくみ、水が溜まる腹水などの症状が起こります。
クモ状血管腫
毛細血管が拡張すると、赤くクモの脚のような形で盛り上がってみえます。特に、肩や二の腕、胸などに起こりやすいです。
手掌紅斑
手の親指や小指の付け根部分に紅斑が現れます。手掌紅斑は、痛みやかゆみなどの症状はありません。
女性化乳房
乳房や乳首が大きくなる症状で、男性にみられます。男性の体内にある女性ホルモンの代謝低下が原因で起こります。
出血
肝臓機能の低下によって血液を固める凝固因子の生成が減少すると、血が止まりにくい、出血しやすいといった症状が現れます。
肝硬変の検査
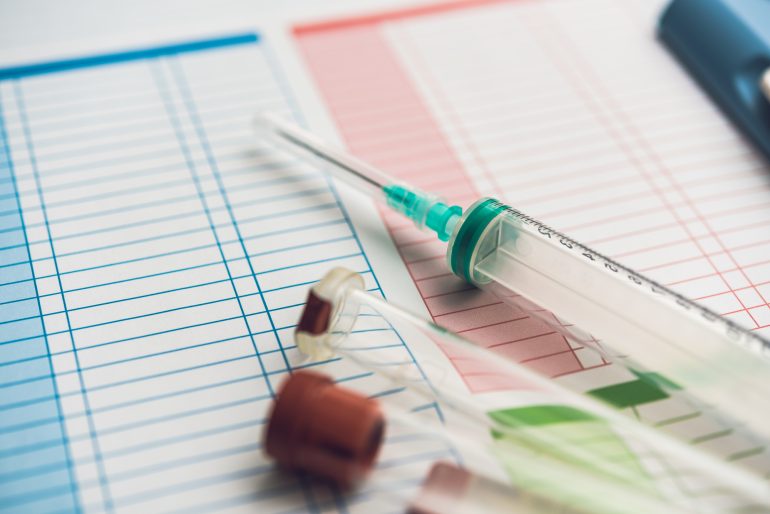 肝硬変は、血液検査や腹部エコー検査で診断が可能です。
肝硬変は、血液検査や腹部エコー検査で診断が可能です。
血液検査では、GOT[AST]、GPT[ALT]の値を測ることで診断することができます。GOT[AST]が正常よりも高い場合、肝硬変の疑いがあります。
腹部エコー検査では、肝硬変特有の硬いゴツゴツとした形状がみられます。また、脾臓の腫大、腹水なども画像で確認することができる場合があります。
肝硬変の治療
代償性肝硬変(初期の肝硬変)の治療
日常生活で特に支障が出ていない場合は、栄養バランスの整った食生活を心がけ、生活習慣の改善を行いましょう。
定期的に血液検査や腹部エコー検査で経過観察を行いながら様子を見ます。
非代償性肝硬変(中期~末期の肝硬変)の治療
腹水の治療
食事療法、栄養療法で水分や塩分を制限する必要があります。また、状態によっては利尿剤の使用を検討します。肝硬変によってアルブミンの生成が低下するので、アルブミン注射を行う場合があります。肝臓に負担をかけないよう安静に過ごすことが大切です。
食道静脈瘤
肝臓から食道静脈へ流れる血液が逆流してコブのような静脈瘤ができることがあります。特に痛みなどの症状はなく、小さいものであれば自然に治ることもありますが、静脈瘤が破裂しないように経過観察を行う必要があります。静脈瘤の破裂を防ぐために、Oリングと呼ばれる輪ゴムのようなものを内視鏡を用いて縛って、血管に硬化剤を注入して固める方法があります。
肝性脳症
肝臓の機能が低下することで、肝臓で除去されるはずの毒素アンモニアなどの有害物質が血液中に溜まって脳に到達すると、肝性脳症を発症します。安静に過ごしながら、栄養療法や下剤、薬物療法で治療を行います。
肝硬変を予防するために
肝硬変は、B型肝炎やC型肝炎の感染によって発症することがほとんどです。まずは、B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスに感染しないために、感染者から血液や体液を介して感染するのを防ぐことが重要です。
肝硬変は、進行してから自覚症状が現れるため、発見の遅れにつながります。そのため、定期的な検査で肝臓の状態を把握しておくことで、肝硬変の予防や早期発見になります。
肝硬変だけでなく、肝臓病全般に言えることですが、過剰な飲酒は肝臓に負担をかけて発症リスクが高くなります。普段からお酒をよく飲む方は、アルコールの量に注意しましょう。
アルコール性肝炎の方は、禁酒や生活習慣の見直し、食生活の改善を行いましょう。飲酒をしていない方も発症する非アルコール性脂肪性肝疾患は、脂肪分の多い食事や運動不足が発症の要因となるため、食生活の改善や適度な運動を行うようにしましょう。
肝硬変を予防するための食事
 栄養バランスの整った食事は、肝機能の回復に必要となります。
栄養バランスの整った食事は、肝機能の回復に必要となります。
腹水やむくみがある場合、塩分や水分の摂り過ぎに注意してください。食事療法や薬物療法で腸内環境を改善することが大切です。
糖尿病などの合併症がある方は、砂糖や果物などの糖質の摂り過ぎに注意してください。また肝性脳症がある方は、タンパク質の摂取を控え、アミノ酸製剤で不足したタンパク質を補うことが推奨されています。
食道静脈瘤がある方は、刺激の強い香辛料や固形物は破裂の原因となるので控えましょう。
肝硬変によって、肝機能が低下すると解毒作用も弱くなります。
そのため、肉、魚、卵は必ず火を通してください。アルコールは、肝臓に負担がかかるので控えましょう。
便秘の方は、肝性脳症の発症リスクが高いので、便秘を改善するために食物繊維を食事に取り入れましょう。